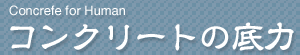松重閘門(愛知県名古屋市)
名古屋市内の南西部にたたずむこの閘門は1930(昭和5)年の竣工。古くから名古屋の水運物流を担った歴史を持つ堀川と名古屋港、笹島貨物駅を結ぶ水運施設として中川運河の水位調整を目的に建設。SRC造、塔高約21mで、人造石塗り洗出し仕上げ(一部花崗岩張り)が施されている。水路の水位差が1m強あり、船の往来時は、まず船を水門から全長90.9m、幅9.1mの水路に入れた後、水門の開閉で水位を整え、約20分後に水門を開けて通した。最大 60t級の船も航行可能で完成当時は「東洋のパナマ運河」とも謳われ、2基1組、計4本の尖塔は最上階にゴシック風の屋根を付けた見張り台を設けるなど、ヨーロッパの古城を思わせる重厚な外観でひときわその存在感を誇った。
供用から約半世紀を経て閘門としての機能は、ピリオドを打ったが、市民の強い要望で永久保存が決定。周囲を含めて「松重閘門公園」として生き残り、夜間にはライトアップされ「水上の貴婦人」ともいうべきエキゾチックなシルエットを際立たせている(1986年、名古屋市文化財指定、1993年、名古屋市都市景観重要建築物指定)。