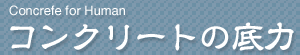日本初のRC橋(京都府京都市)
日本最初のRC橋として、また我が国土木コンクリート発展の原点として多くの文献等でも紹介され、つとに有名なメラン式弧形桁橋。大きさは、橋長 7.3m、幅1.5m、桁厚約30cmで緑豊かな琵琶湖疏水第三トンネル東口付近にたたずむ(上写真)。
東京遷都以降、かげりが見えた京都を近代都市に変革すべくその起爆剤として始動した大プロジェクト、琵琶湖疏水建設事業。これを先導したのは田邊朔郎 であった。第一疏水建設を現場で総指揮した彼はコンクリートの本格的研究のため、当時、非常に貴重だった国産セメントを使用し、1903(明治36)年に 試作したのがこの橋。建設当時から欄干がなく、現在では転落防止用の柵が配置されている。この橋での経験をもとに翌年には、この橋からほど近い第二トンネ ルそばに日本初の実用RCアーチ橋「御陵黒岩橋(橋長8m)」(下写真)を完成させ、その後のコンクリート技術の進展の確固たる礎をしるした。
この両橋をはじめ、近代日本の社会基盤・産業インフラ整備の足跡が刻まれた琵琶湖疏水周辺は、日本のコンクリート技術の魁と明治期の技術者魂が感じとれる格好のルートになっている。