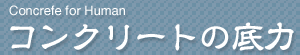黒川発電所・膳棚水路橋(栃木県)
栃木県那須町稲沢地区にある膳棚水路橋(ぜんだなすいろきょう)は、1918(大正10)年の竣工で黒川と余笹川から取水され、那珂川合流点近くで稼動 する黒川発電所までの延長5.1kmにわたる導水路の一部である。そのほとんどは山中を通る導水トンネルだが、当地周辺は水田が広がる平地のため高さ 4.5mの導水橋が架けられた。
鉄筋コンクリート・ラーメン構造の水路橋は、当時まだまだ高価だったセメント・コンクリートを節約するために、水路橋壁は三角のバットレスで補強、橋長 100.6mを支える6.06mスパンの16径間で支える橋脚もスレンダーな3本足に補強のためのX形に筋交いの入った特殊な構造。経済性と機能を優先し た結果のデザインは当時の技術者たちの努力と苦労が偲ばれるが、いま改めて眺めても,他に類を見ない希少性に富み、また優れた景観となって周囲に溶け込ん でいる。