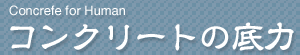白岩砂防堰堤(富山県)
東は3000m級の山々が連なる立山連峰、南は飛騨の山岳地帯、北は水深1000mの湾に囲まれた地形をもつ富山平野。そうしたダイナミックな地形は長い年月のなかで幾度かこの地の人々に大きな試練を与えてきた。幕末1858年に発生した飛越大地震で立山カルデラの鳶山で大崩壊が発生。その崩壊土砂は4.1億m3とも言われる膨大な量で現在でもその約半分が不安定土砂としてカルデラ内に堆積。豪雨のたびに濁流となり平野を襲う土砂の恐怖に立ち向かう地元の本格的な砂防事業の歴史は100年を超える。河口から約42km、常願寺川の支川に位置する白岩砂防堰堤はコンクリートを主体とした高さ63mの主堰堤と7つの副堰堤で構成、全体の落差は108mと日本最大級のもの。1929年に着工した工事は困難を極めた。想像を絶する大量の土砂と厳しい気候条件、隔絶した山中での作業と言う難題をデリッククレーン、ベロセメント、コンクリートミキサ、インクラインなど当時最新鋭の技術で克服し1939年に完成した。堰堤は供用から70年以上も経て常願寺川水系砂防の要としてその機能を発揮、自然と折り合いをつけ「コンクリートが人を守る」を体現している(1999年、国の登録有形文化財指定)。