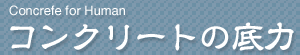普代水門と太田名部防潮堤(岩手県・下閉伊郡)
東日本大震災による巨大津波の来襲にあっても地区住民の命を守りきったのが普代水門(1984年完成,総延長205m、高さ15.5m、写真上)と太田名部防潮堤(1970年完成,総延長155m、高さ15.5m、写真下)。
岩手県太平洋岸北部に位置する普代村では、1896(明治29)年と1933(昭和8)年の大津波で合計439名もの犠牲者を出した。この苦い経験を肝に銘じた当時の村長、和村幸得氏は1960〜70年代にかけての堤防整備計画で明治三陸大津波の高さが15mに達したとの言い伝えをもとに高さ15.5mでの堤防建設を打ち出したが、この方針に村の賛否が大きく割れた。紛糾した議論を制し建設を貫いた村長の信念の正しさは、着工から約40年を経て恐ろしいほどに巨大な自然の力を耐え抜くことで明白となった。
運命の3.11。普代川河口から300m上流にある水門には門高を超える20m近い大津波が押し寄せて上部の機械室に侵入し越流。しかし水門により勢いを失った水流は300mほど内陸を侵した地点で流れを止め,住居地区への侵入を防いだ。関係者の信念と勇気が造り上げたこの水門と防潮堤は、「人のためのコンクリート」を示す歴史の生き証人のひとつとなっている。