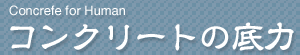岩手県公会堂(岩手県・盛岡市)
東北における近代コンクリート建築の先駆として知られるこの建物は、昭和天皇のご成婚を記念して1925(大正14)年に着工、RC造地上2階、地下1階、延べ面積3589m2の規模で1927年に竣工した。設計は、都市景観設計の第一人者であり東京の日比谷公会堂や早稲田大学大隈講堂を手がけた佐藤功一が担当。外観は茶色のスクラッチタイル貼り、外側に張り出した柱を際立たせる垂直性のフォルムで一連の作風をストレートに感じ取ることができる。
竣工当時は、県会議事堂、大ホール、料理店、皇族用宿泊所の機能を集めた多機能施設として運営され、正面中央に配された高さ約24m、6層の塔屋からは盛岡の街を一望できたという。
正面入り口2階には昭和天皇を迎えて行われたと言う陸自大演習の際の「大本営・御座所」が残る。館内は大小14の会議室や大ホールなどで構成、最盛期には地元の文士劇や演劇、コンサートなどが催され多くの市民に親しまれた。
大規模な補修もなく80年を超える歴史を刻んできた建物の内部には、漆喰の美しい装飾など当時の面影を伝えるデザインが随所にうかがえる。一時期は維持管理問題から存廃論議に揺れた時期もあったが、現在は館内の一部をテナントルームに転用し県内のNPOなどが入居。これからの街の発展を考える重要な情報交差点としてもその役割を果たしている(2006年、国登録有形文化財)。