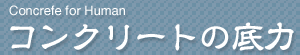東西用水酒津樋門(岡山県・倉敷市)
倉敷の発展史を語る時、欠くことのできない高梁川が運ぶ大量の土砂との戦い。江戸期には天領として栄えたこの地も、その陰では干拓による生活基盤確保と洪水に備えた築堤造りの苦闘が繰り返された。ようやく近代土木技術による抜本的対策の手が付けられたのは明治後期に入ってからのこと。1911年に内務省直轄で始動した高梁川改修事業は、フランスで近代土木建築学を学び、後に港湾治水の祖と謳われた沖野忠雄技監が陣頭を指揮した。工事では全長24kmの堤防構築とともに干ばつ時に頻発した農業用水争いを鎮めるため川の両岸にあった11個所の取水樋門を統合、用水を経済的かつ公平に配分する新たな樋門をRC造で建設した(1924年竣工)。樋門は取水樋門、北・南の配水樋門からなり、表面に花崗岩をあしらった風格ある造りで、農業用としては国内最大級を誇る。取水樋門をくぐった水流は約3.1haの配水池に導かれた後、21の配水樋門から6つの用水路に分配される。供用後90年以上を経て人の営みと自然、そしてコンクリートの役割を巧みに調和させて、今もここに集う豊穣な農地づくりのための力水の脈動を支え続けている。