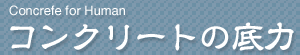淀屋橋(大阪市)
淀屋橋(よどやばし)は、大阪市の中心部を南北に縦断する御堂筋の、土佐堀川に架かる三連の鉄筋コンクリート造アーチ橋である。周辺には大阪市役所、図書館、銀行、オフィスなどが並び、交通の要衝として市民生活・経済活動の要に位置する。
橋名の由来は、江戸時代初期に活躍した豪商淀屋が初代の木橋を架け、管理したことによると伝えられている。
現在の淀屋橋は、橋長53.5m、幅員37.6m、6車線を持つ大動脈として1935(昭和10)年に大阪市の第一次都市計画事業で架けられた。1958(昭和33)年には国道25号に指定されている。
橋のデザインは、すぐ北側の堂島川に架かる大江橋とともに、一般からの懸賞募集によって採用されたものである。躯体側面に花崗岩を施す重厚な外観や高欄の半円アーチ形を用いた幾何学的な意匠など、昭和初めの雰囲気をよく残しており、橋梁デザイン史上での価値が高い。また、周辺地域との調和も図られており、水都大阪を象徴する景観の一つといえよう。さらに、この橋は地下鉄と一体的に建設された特殊な工法による基礎構造を持っており、当時の技術レベルを示す遺構としても貴重である。
これらのことが認められ、淀屋橋は大江橋とともに2008(平成20)年に国の重要文化財に指定された。国道の橋梁では、日本橋(東京都中央区、石造)、萬代橋(新潟県新潟市)に次いで、全国で3例目である(コンクリート造としては2例目)。
大阪市営地下鉄や京阪電車の駅名にもなっている淀屋橋であるが、地下鉄駅の利用者だけでも一日20万人にものぼる。加えて、自動車や自転車、歩行者も含めた大勢の人々が、毎日無意識のうちに橋の名前を目にしたり聞いたりしていることだろう。
架橋後80年近くが経過したが、淀屋橋は今まで同様健全に第一線で活躍している。一方、橋を渡る人々や車には隔世の感を禁じ得ない。淀屋橋にはこれからも水都大阪を水辺から末永く見守っていただきたいと願うものである。まさに明日に架ける橋である。